
|
|
|
| 製品情報 | トピックス | お問合せ | サポート | 会社情報 | ダウンロード | 人材募集 | イベント/展示会 | リンク | |
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
緊急地震速報受信システムは、気象庁が提供している緊急地震速報を受信し、この情報をもとに受信場所における予測震度や大きな揺れの到達時間を推定し、報知するシステムです。 大きな揺れが到達する事前情報として、地震災害の低減に寄与することができます。 |
|||||||||||
| ◆特長 |
・衛星通信でも地上回線にも対応(それぞれ専用受信器が必要)できます。 ・震源位置、主要動が到達する猶予時間、予想震度がデイスプレー上にビジブルに表示されます。 ・警報接点を持っており、ブザー、警報灯をはじめとする他の機器の制御ができます。 ・確認用地震計を併設することで実測値からの制御も行うことができます。 |
||||||||||
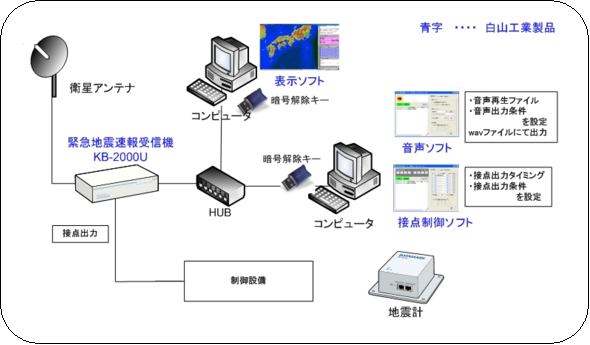 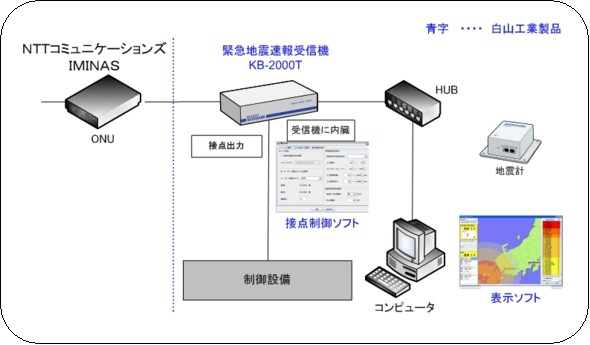 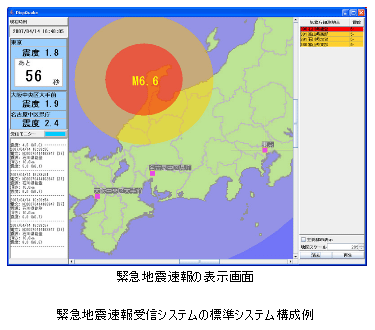
|
|||||||||||
| ページの先頭に戻る | |||||||||||
|
|||||||||||
|
「W-seis」は、地震発生後の救助活動におけるレスキュー隊員の安全確保を計る目的で開発した地震検知・警報システムです。 地震災害現場で余震によるP波をいち早く検知して警報で報知し、主要動が到達する前に作業員待避するための猶予時間を提供します。 |
|||||||||||
| ◆特長 |
・雑振動の多い災害現場で地震と雑振動を判別するため、以下のA,B,CのAND で判定します。 A センサーには速度計を使い、地震と雑振動を区別するためローパスフィルターを通します。 B 振動の継続時間を考慮して、振動の継続時間の長い振動を抽出します。 C 数10m離れた場所3箇所に地震計を設置し、3箇所中2箇所以上でトリガーが掛かった場合 ・地震を検知した場合、回転灯とサイレンで警報を発します。 ・現場の環境や操作性を考え、システムの操作は、検知レベルのみスイッチで切替可能です。 |
||||||||||
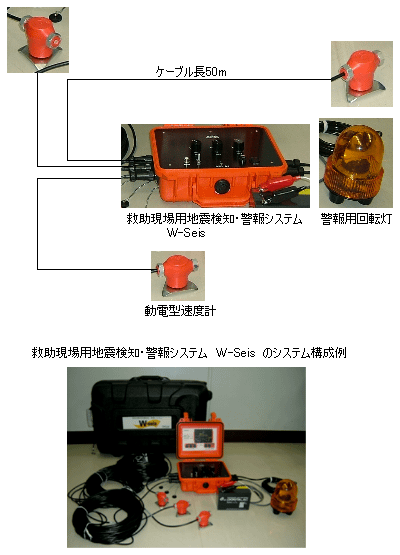
|
|||||||||||
| ページの先頭に戻る | |||||||||||
|
|||||||||||
|
半導体工場や自動車、鉄鋼、化学プラント、電気、石油、ガスなどのエネルギープラント、鉄道、ビル管理、病院、防災関係機関、津波の遡上を防ぐための水門など、大地震に襲われた場合、一刻も早く地震を自動で感知して、プラントの停止など、減災のための準備工程に入ることで、作業員の安全とプラントの被害を軽減することが求められます。 D-Seisはこのような目的に最適の地震防災・減災用装置です。緊急地震速報と組み合わせることによって、効果は倍増します。 |
|||||||||||
| ◆特長 |
・1秒毎に、最新の揺れ情報を把握し、規定の警報レベルに達した場合、時間の遅れを 生じることなく、警報を発信、表示されます。 ・地震情報は、計測震度相当値の他に3成分合成最大加速度と水平合成SI値も表示され、 その全てを警報出力に設定可能です。 ・震度演算は気象庁アルゴリズム計算式に基づいて行います。 ・表示は、大型LEDを用いる事で視認性とメンテナンス性を高めました。 ・ネットワーク用IPによる地震情報などのデータ転送が可能で、企業防災など社内LAN などを使用し地震情報の共有化が図れ、復興体制の確立にお使いいただけます。 ・各種センサーとの組合せが可能。 (現在ご使用の地震計の表示部のみ交換も可能です。要相談) |
||||||||||
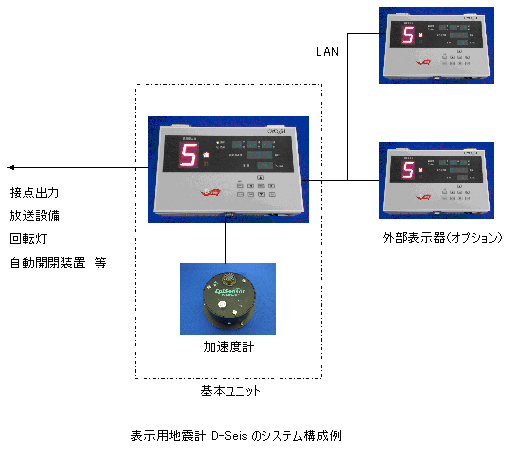
|
|||||||||||
| ページの先頭に戻る | |||||||||||
|
|||||||||||
|
近年、大型の地震による長周期地震が話題になっています。 超高層ビルが長周期地震によって揺すられた場合、非常に大きな揺れになる可能性があります。 超高層建物に予め地震計を設置して、地震の揺れを把握すること、揺れの状態をリアルタイムで把握して、ビルの居住者にネットワークで伝達し、地震によるパニック発生を未然に防ぐなどの対策をお考えの場合、M-Seisが力強い見方になります。 超高層ビルは台風による揺れも記録し、長周期地震の場合と同様に、減災に役立てることが可能です。 |
|||||||||||
| ◆特長 |
・AD変換器内蔵型の加速度計(最大24チャンネル)と中央の処置・表示装置から成ります。 ・センサーとして、加速度計の外、風向・風速計も接続できます。 ・24ビットΔシグマAD変換器を使用、実効18ビットの分解能を有します。 ・サーボ型加速度計TA-25を使用、1mgalの分解能を有します。 ・総合周波数特性はDC~40Hzでフラット(-3dB)、総合分解能7.6mgalです。 ・トリガー後、10秒毎に震度、SI値、最大加速度等を出力でき、ネットワーク上のPCで受信できます。 ・建物のリアルタイムの揺れを可視的に表示でき、地震時の揺れを後で表示できます。 ・トリガーとデトリガーを別個に設定可能で、地下階の地震計でトリガーをかけ、 最上階の地震計でデトリガーをかけることが出来ます。 ・加速度波形は、ヘッダー付き多チャンネルファイルで記録されます。 ・時刻校正は、GPSによる校正の外,FM時報による校正も可能です。 ・3chセンサーユニット間の時間差は、10-2 秒、3chセンサーユニット内の時間差はありません。 |
||||||||||

|
|||||||||||
| ページの先頭に戻る | |||||||||||
|
|||||||||||
| 原子力発電所、火力発電所、超高層建物など、長大重要構造物の地震時の揺れを多チャンネル、高精度で記録し、構造物の長期的管理に使用すると共に、地震時の被災判定、緊急対策の基礎データとすることをお考えの場合、Graniteによる多チャンネルシステムが最適です。 | |||||||||||
| ◆特長 |
・Graniteはキネメトリックス社の新シリーズROCKシリーズの多チャンネル地震動観測システムです。 ・最大36チャンネルの入力が可能、これを超える場合、複数台のGraniteを組み合わせて、 100チャンネルを越えるような多チャンネルのシステムもフレキシブルに構築できます。 ・高ダイナミックレンジ(155dB)加速度計EpiSensorと高性能(128dB)レコーダの組み合わせにより、 微小レベルの振動から、震度7の強震に至る幅広い記録を収録できます。 ・サンプリング間隔は1Hz~2000Hzで10通りの設定が可能で、同時に複数の設定が可能です。 これにより、加速度計の外、風向・風速計等の低いサンプリング速度のセンサーも接続できます。 ・リアルタイム波形出力の機能を有しており、地震波系収録の機能に限らず、 リアルタイム地震防災の用途で使用することも可能です。 ・高度な電源設計により低消費電力を実現していますので、停電時、災害時等悪い条件の下での 地震動観測を継続する上で格段に有利です。 ・キネメトリックスの標準フォーマット(evtファイル)や日本標準のwinフォーマットなど 様々なフォーマットのデータを出力フォーマットとして指定できます。 |
||||||||||

|
|||||||||||
| ページの先頭に戻る | |||||||||||
|
|||||||||||
|
国土交通省強震計ネットワーク 国土交通省では、地震直後所管の河川・道路施設の緊急点検の必要性や被災状況の予測評価など、初動における施設管理者の意志決定の支援を目的として、 全国に地震計ネットワークを整備しています http://www.nilim.go.jp/japanese/database/nwdb/index.htm 弊社の強震計ETNA-SIはこのネットワークで多数使用されています。 このほど、ETNA-SIの後継機種として、K-SEIS 100を開発しました。 |
|||||||||||
| ◆特長 |
・K-SEIS 100 は、国土交通省の強震計仕様に適合し、通信仕様に留まらず、筐体寸法も同一仕様として、 既往強震計の更新によるコストを最小限とする設計にしつつ、最新技術を多数搭載しています。 ・国交省の強震計仕様と共に、気象庁震度計仕様を併せ持っており、震度計検定品です。 ・通信機能としては、ダイアルアップ接続およびIP接続による通信が可能です。 ・トリガー方式と共に、リアルタイム波形伝送の機能を有し、リアルタイム防災に適しています。 ・センサには±4G、155dBのダイナミックレンジを持つフォースバランス型加速度計を採用し、 135dBの高ダイナミックレンジと拡張性の高い通信機能を持った強震計であり、 高精度な強震観測や地震情報ネットワーク用としての適しています。 |
||||||||||
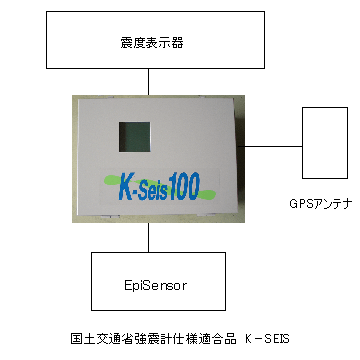
|
|||||||||||
| ページの先頭に戻る | |||||||||||
|
|||||||||||
|
E-キャッチャー は名古屋大学、愛知工業大学、㈱東海理化、応用地震計測㈱が共同で開発した小型地震計です。 半導体センサを用いた小型強震計でありながら、本格的な強震計に求められる殆どすべての機能を有します。 地震波形を収録する機能はもちろん、震度相当値、SI値をリアルタイムで計算してLANポートから出力機能を有します。 震度相当値は本体側面の小型LEDに表示されます。 |
|||||||||||
| ◆特長 |
・専用の小型表示器と組み合わせて、廉価な震度計として使用できます。 ・複数台の連動機能があり、一般の建物や免震建物の地震時の地震動波形の観測に最適です。 ・無電圧接点3ポートを有し、地震時に設定震度で警報を発信でき、リアルタイム地震防災情報システムを構築できます。 ・緊急地震速報と併用することにより、信頼性の高いリアルタイム地震防災システムを構築できます。 ・イントラネットに接続して、廉価な地震計ネットワークを簡易に構築できます。 ・台車式振動台と組み合わせることにより、各種震度の揺れを簡易に体験出来、防災教育ツールとして使用できます。 |
||||||||||
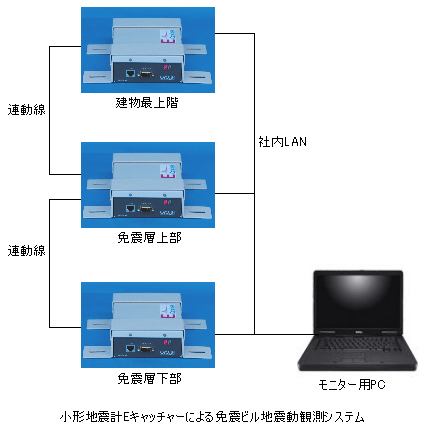 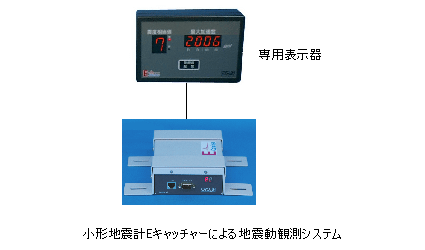
|
|||||||||||
| ページの先頭に戻る | |||||||||||